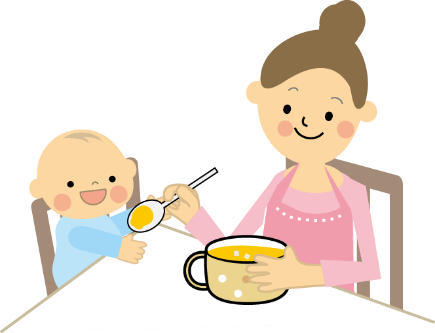~利用してみたいなぁ・自分もお手伝いしてみたいなぁ~
近年 核家族化は進み、夫婦共働きの自立世帯が増えています。子育て家庭への支援は手厚くなっていますが、そのサポートは住んでる地域の自治体で決められており、同じではありません。まずは お住まいの地域にあるファミリー・サポート・センターに問い合わせてみましょう。

目次
1. ファミリー・サポートとは
子どもがいる家庭の方は最近よく聞くと思いますが、
「ファミリー・サポート・センター」(略してファミサポ)

*「病院に行きたいけど その間 赤ちゃんを見ていて欲しい」
*「産前産後の上の子と遊んでくれる人はいないかしら」
*「子どもの塾の送迎 頼みたいわ」 などなど
ほんの短時間 誰かのサポートがあれば ずいぶん助かるという場面 
そんな子育て中の 助けが欲しいご家庭(依頼会員)に
お手伝いをしてくれる地域の方(提供会員)を紹介するのが
ファミリー・サポート事業です。
最近増え始めた
「助けも欲しいけど、空いている時は私が他の方を助けるわ」という
両方会員さんもいます。
私は子育て支援センターで 親子の交流事業を中心に働いていましたが、
異動で2年間 ファミサポのアドバイザー(依頼会員に提供会員を紹介する)をしていました。
「子育て支援」分野に長くいましたが、知らないことはいろいろあるもので、
とても勉強になった2年間でした。
「ファミリー・サポート・センター」の歴史は長く、
核家族化が進み、平均寿命も延び、元気なお年寄りが増えた現代。
健康で社会貢献したい 経験を活かしたい高齢者の力を生かすべく
1980年「シルバー人材センター」が設立 (でもおじ様が中心)
その後 働く人々の仕事や子育て、介護を応援すべく
労働省(当時)が後押して、
1994年「女性労働協会」が設立され、
現在の形となっています。

少数ですが、地域によっては 介護のサポート依頼 続けているところもあります。
2. まずは会員登録
設立運営は各市町村なので、
地域の実情・財政(?!)に合った、それぞれの仕組みが作られています。

そして、これは有償ではありますが、あくまでボランティアですので、
できること、出来ないことの区別があり、また 同じ地域に住む方々の相互援助ですので、
気持ちよい援助をすべく、良識を持ったお付き合いが大切になります。

*会員登録を行う説明会は、各市町村の広報誌で確認してください。
例 ・月に1~2度のところ
・地域の様々な場所に出張して行うところ などなど
登録は無料なので、出産や入院、入塾が決まってるなど 援助が決まっているときは、
早めに登録をしておくことをお勧めします。
3・4月は入学・入園などに伴う新しい援助希望が多く、 登録→紹介までに時間が掛かることがあります。
援助の内容(曜日・時間・場所も含む)ができる方を探し、
「人見知りがあって」とか
「やんちゃな男の子で、体を動かすのが大好き」など
お子さんの性格や個性に寄り添える、提供会員さんをお探しするので、
アドバイザーは熟慮します。


3. 提供会員はどうやってなるの?
まず、会員登録(地域在住のみ、地域在住&通勤・通学など様々)
その後 お子さんを預かる為の講座を受講します。(講座が先の地域もあり)
基本は保育援助前におさえておきたい 9項目24時間
こどもが成長して手が離れたママたちやシニア世代は なかなかお忙しく
都合をつけるのは難しい。
1日 6時間でも4日間 びっしり!!


そこで各センターは工夫して、
保育内容についてやケガ・病気、支払いなど
特に要注意点の講習を最低限行い、
援助を開始しながらフォローアップの講座を開いているところもあります。

講習会は、会員の都合に合わせ、単位制で受講。 連日参加の方もいれば、1年かけて受講する人もいます。

例 A市 午前中のみ10日間
B市 午前・午後 2日間
C市 午前・午後 6日間
また 2015年に子育て支援員制度を国が新設し、
より様々な保育分野で活躍できるように
基本の保育援助分野に加え、障害や乳児など専門分野も講習会に入れている自治体もあります。
4. 援助するお子さんの年齢は? 料金は?
*お預かりする年齢も地域によって様々です
例 ・生後43日~小学校6年生まで
・1歳の誕生日を迎えてから 小学校6年生まで
*活動の時間帯や値段も違います。
A市
| 活動 | 時間 | 料金 |
| 月~日(祝日・正月含む) | am7 ~ pm10 | 800円/時間 |
*病児・病後児の預かりは無し、交通費・食事代等は別
B市| 活動 | 時間 | 料金 |
| 月~日(年末年始以外) | am7 ~ pm7 | 800円/時間 |
| 月~日(年末年始以外) | am6~7
pm7~10 |
900円/時間 |
| 12月29日~1月3日 | am6~pm10 | 900円/時間 |
| 病児・病後児預かり
(平日のみ) |
Am8~pm6:30 | 1000円/時間 |
5. みんな どんな援助をお願いしてる?
各家庭 援助して欲しい(依頼)内容は色々ですが、
最近多かったのは
1位 保育園・幼稚園の朝の送り、夕方のお迎え
2位 保育園・幼稚園のお迎え&お預かり(食事提供の援助も)
3位 習い事の送迎
他にも 保護者の美容院・通院・買い物中の保育、もちろん 時短を含め、仕事中の保育も。
双子ちゃんや三つ子ちゃんで大変!!
「お食事を一緒に 食べさせて欲しい」っていうサポートもありました。
1位も3位も送迎なのでほんのちょっとした時間(30分~1時間内)ですが、
これが働いているママや、病気・妊娠中のママたち、シングル家庭は助けが欲しいのです。

6. 援助までの流れ
基本の流れ
ファミリー・サポートは人と人とのつながりなので、フィーリンが合わないこともあります。
そんな時はアドバイザーに相談すると 両者の間に入って、次の会員さんをご紹介します。
相性が合うと お子さんも安心してファミサポさんとの時間を楽しめます。
送り迎えの合間に 学校であったことや親には言えないお友だちとのけんか話なども・・・
私が担当してた時
「赤ちゃんから援助していた子が中学生になって制服姿を見せにきてくれたのよ」と
提供会員さんが嬉しそうに話してくれたこともありました。
良い時間を過ごして来たんでしょうね。
援助の内容によっては、保育園や幼稚園の一時預かりの方が安い場合もあります。

近年 待機児問題などあり、子育て支援のサービスも充実してきました。
ファミサポやベビーシッター、園の一時預かりの利用に対し 助成金の給付も始まっています。
会社の福利厚生で、補助費が出る ステキな会社もあります。
日本の補助制度(特にお金が絡むもの)は 自分で申請しなければ受け取れないので、
ぜひ お住いの役所や保健センターへ問い合わせてみましょう。
情報収集力は子育て世代には大事なスキルです。
ファミサポ利用の際は「住んでる地域のセンターに聞いてみよう!!」

他の市区町村との会議に行くと 本当ビックリすることばかり。
値段が違う、援助の制限が違う、・・・
でも 地域のマンパワーを借りるわけですから、地域差があるのは仕方がない。
住めば都です。
(隣の芝生は青いならぬ 隣の市は子育て支援が充実。なのに・・・)なんて思わずに
楽しく子育てライフ そして シニアライフ楽しんで欲しいです。
ぬっぺ/NUPPE